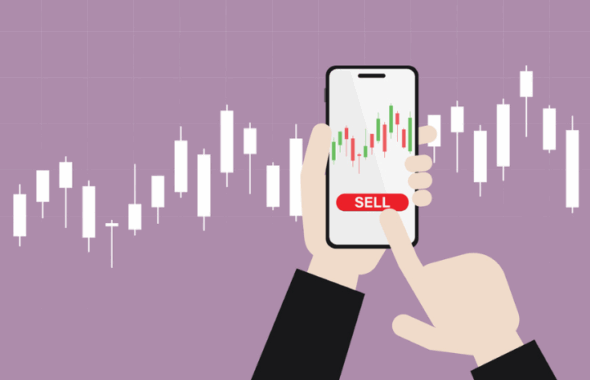日本の景気に関わる注目すべきイベントと指標には何がある?
株価や為替レートは、日々上下に動いています。その動きの理由のひとつに、日本の景気があります。景気がよければ(上向くと予想できれば)株価は上昇し、為替レートは円高に動く傾向がみられます。この景気を判断するためのさまざまなイベントや指標が、日本・米国など各所で発表されています。投資家のなかには、これらのイベントや指標に注目し、投資判断をしている人もいます。
日本は主に米国の影響を強く受けます。よって、日本だけでなく、米国の動向を把握することは超重要です。
今回は、マーケットの変動に影響を与える注目すべきイベントや指標にはどんなものがあるのか、紹介します。
注目すべきイベント①日銀金融政策決定会合
日本の中央銀行、日本銀行(日銀)が金融政策を決めるために開催する会合です。年8回、それぞれ2日間開催されます。参加者は日銀総裁、副総裁(2人)、審議委員(6人)の計9人。2025年時点の日銀総裁は植田和男氏です。
金融政策決定会合では、日本の景気の状態や金融政策について話し合われ、政策金利が決められます。政策金利とは、景気や物価などをコントロールするために設定される金利のことです。
景気がよく、収入や消費が増えると、物価が上昇(インフレ)します。程よいインフレなら問題ないものの、インフレが加熱しすぎると、給与よりも物価が常に高い状態となり、国民の生活が苦しくなっていきます。そこで日銀は、政策金利を引き上げてインフレを抑え込もうとします。こうした政策を「金融引き締め政策」といいます。
また、景気が悪く物価が下落(デフレ)傾向にあるときには、政策金利を引き下げて景気を刺激し、物価を上げようとします。このような政策を「金融緩和政策」といいます。
私たちが利用する預貯金や住宅ローンの金利は政策金利をもとに定められますので、とても重要です。
また、政策金利の上昇は、企業が銀行から借りるお金の金利が上昇することにもつながりますので、一般的には株価の下落要因になります。そのため、金融政策決定会合の結果や政策金利の変動は多くの投資家が注目しています。なお、金融政策決定会合で決定した内容は2日目にすぐ公表されます。
【最近の動向】
日本は長らく「マイナス金利政策」をとってきました。日本のマイナス金利政策は、日銀が民間の金融機関から預かる預金にマイナス金利をつけることをいいます。民間の金融機関は、日銀にお金を預けると損をしてしまいますので、お金を企業や個人に貸し出そうとします。そこまでして景気を上向かせようとしてきたのです。
日銀は2024年3月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を解除することを決定。さらに、2024年7月・2025年1月の金融政策決定会合では利上げを発表しました。本稿執筆時点(2025年2月17日)の政策金利は0.5%となっています。市場では、2025年中にさらなる利上げがあるかどうかが話題になっています。
【2025年の日銀金融政策決定会合の開催予定】
1月23日・24日
3月18日・19日
4月30日・5月1日
6月16日・17日
7月30日・31日
9月18日・19日
10月29日・30日
12月18日・19日
注目すべきイベント②FOMC(連邦公開市場委員会)
米国の金融政策を決定する会合がFOMCです。日銀の金融政策決定会合の米国版というと、理解が早いかもしれません。FOMCも年8回で、それぞれ2日間開催されます。FOMCの参加者は、米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)の議長(1人)、副議長(2人)理事(4人)と、米国の12地区の地区連銀総裁(12人)の合計19人。2025年時点の議長はパウエル氏です。
米国は世界経済の中心ですから、米国の金融政策の動向は日本を含む世界中に大きな影響を与えます。米国が利上げすればドル高になり、景気の過熱やインフレを抑える方向に作用します。反対に利下げすればドル安となり、経済の活性化による企業業績の拡大が期待できます。市場の予想と異なる「サプライズ」が起きたときにも、市場は敏感に反応することから、FOMCの動向は世界中の投資家が注目しています。
【最近の動向】
ロシアのウクライナ侵攻に端を発するインフレを抑え込むため、米国は2022年・2023年に11回もの利上げを実施。政策金利は5.25%〜5.5%にまで上昇しました。その後、インフレが多少落ち着いたのをみて2024年9月から12月に3回連続での利下げを実施しています。今後も数度の利下げが行われるのではないかという見方が優勢です。
【2025年のFOMCの開催予定】
1月28日・29日
3月18日・19日
5月6日・7日
6月17日・18日
7月29日・30日
9月16日・17日
10月28日・29日
12月9日・10日
注目すべきイベント③ECB理事会
ECBは「欧州中央銀行」で、ユーロ圏の中央銀行です。ECB理事会では、ユーロ圏の政策金利が決められます。ECBも年8回、6週間ごとに開催。参加者は役員会メンバー6名(総裁、副総裁、理事4名)とユーロ圏の中銀総裁19名の計25名です。日本・米国同様、ユーロ圏の金融政策にも注目されます。
【最近の動向】
ECBも米国同様、2022年以降のインフレ対策で政策金利を急ピッチで引き上げました。政策金利は、一時4.5%まで上昇しています。しかし、2024年9月以降、2025年1月まで4回連続で利下げを実施。わずか5か月あまりで政策金利が1.25%引き下げられています。
【2025年のECB理事会の開催予定】
1月30日
3月6日
4月17日
6月5日
7月24日
9月11日
10月30日
12月18日
注目すべきイベント④G20
G20は世界の主要先進国と新興国が参加する会議の枠組みです。具体的には、
・先進国
米国、英国、ドイツ、日本、フランス、イタリア、カナダ、欧州連合(EU)
・新興国
アルゼンチン、豪州、ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、韓国、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、アフリカ連合(AU)
が参加しています。G20の参加国だけで世界経済の8割以上のGDPを占めているため、その内容が日本の景気にも影響を与える可能性があります。近年では、2020年のコロナ禍の際にG20各国が巨額の財政出動を行うことに合意し、世界経済を下支えしました。
G20では、世界経済、貿易・投資、開発、環境、気候・エネルギー、国際保健、デジタルなど、幅広い分野での議論が行われます。年に1回、各国の持ち回りでG20サミットが開催されています。2025年は11月に南アフリカのヨハネスブルクで開催予定です。先進国と新興国の立場の違いなどによる対立がしばしば話題になりますが、問題解決に向けての取り組みが進められています。
注目すべきイベント⑤IMF(国際通貨基金)の世界経済見通し
IMFは国際連合の機関のひとつで、世界の金融市場や為替相場を安定させるために設立されました。IMFは年2回、4月と10月に公表する「世界経済見通し」で、世界や各地域がこれからどのくらい成長するか、その見通しを発表しています(1月と7月には「改訂版」も発表されています)。
<IMF「世界経済見通し」の推移と予測(1980年〜)>
(株)Money&You作成
1980年以降のデータで見ると、年や地域によって多少前後はありますが、世界経済はおおむね年3〜4%成長していることがわかります。2025年1月改訂版によると、2025年と2026年の世界経済成長率は3.3%と予測されています。いいかえれば、世界全体に分散投資していれば、世界経済の成長の恩恵を受けながら堅実にお金を増やすことができることを表しています。
注目すべき指標①米国雇用統計
米国の雇用情勢を調査した統計です。原則として毎月第1金曜日、日本時間の21時30分(夏時間)・22時30分(冬時間)に公表されています。毎回十数項目の統計が発表されますが、特に注目されているのは「失業率」と「非農業部門雇用者数」です。
市場の予想よりも失業率が低かったり非農業部門雇用者数が多かったりする場合は、米国の景気が予想より良いと判断されます。ドルが買われてドル高(円安)となり、米国株も上昇する期待ができます。
反対に、市場の予想よりも失業率が高かったり非農業部門雇用者数が少なかったりする場合は、米国の景気が予想より悪いと判断されて、ドル安(円高)、米国株安の要因になったりすることもあります。
米国雇用統計は、特にFX(外国為替証拠金取引)をしている人が注目しています。場合によっては、発表直後に為替レートが一気に1円〜2円程度上下することもあります。もちろん、このとおりに動かないこともあるので、あくまで参考資料のひとつではありますが、米国の景気動向を知るためによく活用されています。
注目すべき指標②米国の消費者物価指数(CPI)
米国内で消費者が購入するモノやサービスの価格の推移を示す指数です。米国労働省が毎月中旬に公表しています。全体の動向を示す「総合指数」と、総合指数から値動きの大きな食品とエネルギーを除いた「コア指数」の2つが公表されています。
米国でインフレが進むと、消費者物価指数も上昇するため、FRBは行き過ぎたインフレを防ぐために利上げを行います。反対に、消費者物価指数が上昇しておらず、景気が悪化している場合には、FRBは利下げを実施して景気を刺激します。
米国の消費者物価指数は2021年中頃から急上昇。2022年にはコア指数で6%前後、総合指数で7〜9%もの高い伸びを示しました。これを抑えるために、FRBはFOMCで度重なる利上げを行いました。
2024年になり、コア指数は3%台、総合指数は2%台に落ち着いていましたが、11月から2025年2月にかけて総合指数が4か月連続で拡大して再び3%台に乗せています。目下、消費者物価指数の上昇が収まったことで利下げに転じた米国ですが、今後も消費者物価指数が落ち着いているかどうかは見通せない状況です。
注目すべき指標③ISM製造業景況感指数
米国の全米供給管理協会が公表する、製造業の景気動向を示す指標です。米国製造業の購買担当者を対象にアンケート調査を行い、その集計結果が集計されます。受注・生産・雇用などの状況が「良くなっている」から「悪くなっている」を引いた割合が50%を上回っていれば景気拡大、逆に下回ったら景気後退を表すとされています。
毎月第1営業日に公表されることから、景気の先行指標として広く利用されています。
<ISM製造業景況感指数(2021年〜2025年2月)>
(株)Money&You作成
注目すべき指標④米国の長短金利差
金利には、主に1年未満のお金の貸し借りに使われる「短期金利」と、1年以上のお金の貸し借りに使われる「長期金利」があります。長短金利差は文字どおり、長期金利と短期金利の差を表す指標です。
金利はお金の貸し借りをする際の手数料ですから、基本的には短期金利よりも長期金利のほうが高くなります。しかし、景気が悪くなり、金利が下がるときには、長期金利が先に下がります。そのため、長短金利差が縮小したり、ときには長期金利のほうが低金利になったりすることもあるのです。
目安として、長短金利差が1%を下回ると景気減速、マイナスになると景気後退が懸念されます。
<米国の長短金利差(10年国債利回り−3か月国債利回り)>
Federal Reserve Bank of St. Louis(セントルイス連邦銀行)のデータより
青のグラフは長短金利差の推移をまとめたもの。グラフ内で灰色になっている期間は米国の景気後退局面を表しています。長短金利差が下落し、マイナスになった少しあとに景気後退局面がやってきていることが読み取れます。
注目すべき指標⑤日本の消費者物価指数(CPI)
消費者物価指数は日本でも公表されています。日本では、総務省統計局が毎月公表しています。
日本の消費者物価指数には、大きく分けて
・総合指数
・生鮮食品を除く総合指数(コアCPI)
・生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数(コアコアCPI)
の3つがあります。このうち、注目されているのは天候などによる価格変動の影響が大きな生鮮食品を除いた「生鮮食品を除く総合指数」です。なお、米国の「コア指数」にあたるのは、日本の「コアコアCPI」です。
日本でも2021年12月以降、消費者物価指数が上昇しました。生鮮食品を除く総合指数は2023年8月まで毎月3〜4%台の伸びとなっていたのです。米国ほどではありませんでしたが、それでも物価上昇を肌で感じた人は多いでしょう。
物価の緩やかな上昇は景気がよくなっていることを表し、企業収益にもプラスに働くので、株価上昇の要因になりえます。しかし、急激に物価が上昇すると、消費者は買い控えを起こすなどして品物が売れなくなり、経済鈍化の兆候となる場合もあります。
逆に物価が下落しているデフレの状態だと、企業収益はマイナスになりますし、消費者も「いずれもっと安くなるかもしれない」と買い控えを起こすこともあります。株価下落の要因になると考えられます。
注目すべき指標⑥日銀短観
短観は、日銀が全国の約1万社に対して行う統計調査です。年4回、3、6、9、12月にアンケート調査が行われています。各企業の業況の現状と先行きを「良い」「さほど良くない」「悪い」の3つの選択肢から選んでもらい、「良い」から「悪い」を引いた数値が「業況判断DI」として公表されており、よく参考にされています。
米国の「ISM製造業景況感指数」と同様ですが、ISM製造業景況感指数は「50」が基準になるのに対し、景況判断DIは「0」が基準です。プラスであれば景気がよく、マイナスであれば景気は悪いと判断されます。
<日銀短観の業況判断DIの実績>
(株)Money&You作成
コロナ禍から回復をはじめた2021年以降、業況判断DIは徐々にプラスに転じている様子がわかります。とはいえ、大企業・中堅企業・中小企業でその判断は違いますし、製造業か非製造業かでも回復の度合いが異なることが読み取れます。
注目すべき指標⑦VIX指数(恐怖指数)
VIX指数とは「Volatility Index」の略。シカゴオプション取引所がS&P500種指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表しています。今後30日にどの程度価格が変動するかという「変動性」(=ボラティリティ)を示しています。数値が高いほど市場は不安定になり、株価が下落する恐れが生じることから「恐怖指数」などと呼ばれています。平時は10〜20程度になっていますが、たとえば2024年8月の株価暴落の際には、VIX指数が38まで上昇しています。
<VIX指数の推移>
OANDA証券のウェブサイトより
2024年8月2日・5日は日経平均株価が大幅続落。2日間で約6,668円も下落しました。それにあわせてVIX指数も一気に上昇しています。
市場の動きを完全に予測することは、プロであっても不可能です。しかし、これらのイベントや指標を知っていれば、値動きがあるかもしれないと前もって考えることができます。ぜひイベントや指標を覚えておき、投資に生かしていただければと思います。
頼藤 太希(よりふじ・たいき) マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki