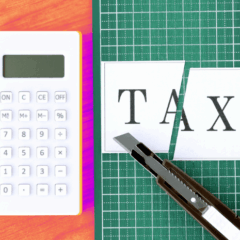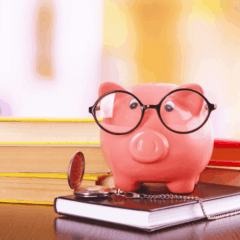【金利上昇の転換期】不動産投資の新たなチャンスと日本経済の未来
日本では長らく続いた超低金利時代が終わり、金利の動向が大きな転換期を迎えています。日銀の政策金利引き上げが不動産購入や日本経済に与える影響を検証し、今後の不動産投資の関係性についても詳しく解説します。
金利上昇がもたらすメリットとデメリットを理解し、投資家にとっての新たなチャンスを見逃さないための戦略を提案します。今回の金利引き上げは、日本の景気回復への本格的な第一歩となるでしょう。
金利の重要性と日銀の役割とは
金利は住宅ローンや不動産投資ローン、銀行の預金金利や企業が融資を受ける際の金利などを始め経済全般へ与える影響も極めて大きいので、日銀は政策金利などのコントロールにより景気の調整を行います。
景気が悪い場合には金利を下げて企業などが資金を調達しやすくしますが、逆に景気が拡大する中では金利を上げて(金融の引き締め)、物価などの上昇を抑えます。
短期金利と長期金利の違い
金利には大きく分けて短期金利と長期金利に分けられます。
短期金利は主に日銀によって決められるので政策金利とも言われています。短期金利は主に住宅ローンや不動産投資ローンの変動型金利と連動したり、普通預金の金利などにも影響します。
長期金利は10年物の国債の利率が基準とされ、市場の動きによって決まります。長期金利は固定型の住宅ローンや不動産投資ローン、銀行の定期預金の金利などと関連があります。
日本の金利動向の歴史。バブル崩壊からアベノミクス、そして最新の金利上昇まで
金利は経済の動きと共に変動してきていますので、近年の金利の動きを振り返ってみましょう。
日本では1990年頃のバブル経済の崩壊で景気が低迷していましたので2000年前後にかけてゼロ金利政策や金融緩和政策が実施されました。デフレ時代は長く続き、2012年に発足した安倍政権による「アベノミクス」でも、基本政策である「3本の矢」の中で低金利政策が実施されました。
その後もデフレ脱却のための低金利政策は続き、2016年には銀行が日銀に資金を預ける金利がマイナスとなる「マイナス金利政策」も始まりました。つまり銀行は資金を日銀に預けておくと損をするため、それだけ融資などに回りやすくする政策でした。
近年では金利は若干上昇傾向となっています。長期金利に関しては変動幅を2021年には0.25%に、2022年12月には0.5%、2023年7月には上限1%、2023年10月には1%を上回る事を容認しています。
2024年3月にはマイナス金利の解除となり、さらに2024年7月には短期金利が0.25%に引き上げとなり、さらに今回の2025年1月に0.5%への追加引き上げとなりました。
◼︎2024年からの短期金利の変遷
| 時期 | 短期金利政策の変遷 |
|---|---|
| 2024年 1月 | マイナス金利の維持を決定 |
| 2024年 3月 | マイナス金利の解除(0~0.1%) |
| 2024年 7月 | 0.25%(上限)へ引き上げ |
| 2025年 1月 | 0.5%(上限)へ引き上げ |
日本経済の未来を見据えた、今後の金利動向と預金金利の上昇
今後の金利動向については物価上昇率2%が持続する中、今年の春闘によるさらなる賃金アップの期待もあり、金利を上げても日本経済に反動が来ないであろうという期待が見え隠れします。
また長期金利も上昇傾向にあり2025年1月後半には長期金利の基準となる新発10年物国債利回りが1.2%前後と高い水準となっています。
こうした金利の上昇を受けて、都市銀行などでは預金金利を引き上げる動きも出ています。UI銀行では1年物の定期預金金利をなんと1%とするなど高い水準となっています。また例えば三井住友銀行では普通預金が2024年8月6日に0.02%から0.1%と引き上げられましたが、今回の金利上昇を受けてさらに2025年3月から0.2%に引き上げると発表がありました。
利息が0.02%ですと100万円を預けても1年間の利息は200円(税別)でしたが、0.2%となると2,000円(同)となる訳です。17年ぶりの高い水準となり、まさに「利息のある世界」に近づいてきていると言えるのではないでしょうか。
今後各金融機関は預金の争奪戦が始まります。今後特に定期預金などは近年では考えられない位の預金金利が登場すると考えます。
ローン返済から市場動向までの影響は
金利上昇が不動産投資に与える影響について見てみましょう。金利が上がれば不動産投資ローンを組んだ場合の返済額が上昇します。また変動型金利ローンを組んでいる場合は、金利が上昇していけば返済額も増加していきます。
今後大きく金利が上昇していけば、現在好調なファミリーマンション市場も売れ行きが滞る可能性があります。また東京23区では平均1億円を超える価格が下がる可能性もあります。しかし地価・建築費は上昇を続けており、こうした影響がもし出るとしてもかなり先の話になるのではないでしょうか。
郊外で住宅ローンを組んで居住用のマンションを購入した層には若干影響があるかもしれませんが、都心の高額マンションは相続対策も含め現金購入層が多く、金利上昇の影響は軽微であると考えられます。
また金利上昇が続けは企業は資金調達が難しくなり、設備投資などの先行投資が滞る可能性もあります。しかも先ほども述べましたが、金利が上昇していると言ってもまだまだ低金利圏にあり、景気の過熱をストップする程の水準にはなっていないので、こうした影響はまだ少ないと考えられます。ちなみにバブル期の金融引き締めの頃は短期金利は8%前後となっていました。その頃に比べると現在はまだまだ非常に金利は低いと言えます。
投資用マンションの返済に与える影響:
投資用マンションのローン金利を2%とすると、金利が0.2%上昇した場合、返済額がどれ位変わるのか見てみましょう。物件価格3,600万円、金利2%、35年返済の場合、毎月返済額は11万9,254円物件価格3,600万円、金利2.2%、35年返済の場合、毎月返済額は12万2,982円増加額はわずか3,728円となります。
金利上昇と不動産価格の関係。賃金アップと資産価値の未来を見据えて
金利が上昇するという事は、諸物価を始め不動産価格が上昇する事を意味します。
金利が上がる前提としては、賃金の上昇や賃金の上昇による購買力のアップ、また多くの現金を保有する資産家にも預金利息の増加、というメリット、また不動産投資家においては金利が上がるという事は返済額の増加を意味しますが、返済額上昇分を賃料に転嫁できる根拠も明白になります。
特に投資マンション市場では、タイムラグはありますが今後家賃の上昇も期待できます。最大のポイントは金利上昇の過程の中では今投資用マンションを買う事で将来の資産価値も保たれやすい、または上昇の可能性があると言えます。
インフレ期の金利上昇と不動産市場。再開発と賃料上昇のチャンスを活かす
金利上昇期はインフレ期である事から、物価だけでなく賃料も上昇する傾向にあります。また景気の上昇により東京などの再開発が増加すれば、不動産市場全体の底上げにもつながります。但しすべての不動産が同じくこうした恩恵を受ける訳ではありません。
景気上昇の恩恵を受けやすいマンションの条件は下記のような条件などを満たす事が重要となります。
- 交通利便性が良い(都心までの距離・駅からの距離など「時間」に優れている)
- 生活利便性が高い(公共機関はもとより医療施設、商業施設が充実している)
- 将来性が高い(近隣もしくは沿線上に再開発等があればよりベター)
- 安全性が高い(耐震性・耐火性はもとよりセキュリティが充実している)
- 居住性が優れている(共用部・専有部共に優れた設備・仕様となっている)
金利上昇と財政への影響。国債利払いから社会保障、不動産投資までの展望
またマクロの視点から見ると、金利上昇により政府が発行している国債の利払いが増加し、財政が悪化する可能性もあります。金利上昇により国債の利払いが増加し、財政が悪化すれば、私達の年金などの社会保障についても影響が出る可能性もあります。
日本の金融資産は約2千兆円ですが、そのうち現金・預金などは1,116兆円(2024年12月現在)です。日本人一人当たり平均では約1,000万円弱となります。仮に1,000万円を普通預金に預けても金利が0.2%なら年の利息はわずか2万円程度となり、金利が上がっても老後の豊かな暮らしには程遠いものがあります。
現在政府では将来のための自助努力としてNISAやiDeCoなどの投資を推奨していますが、年金不安から将来のための不動産投資の需要も増加する可能性もあります。
しかし逆に地価・建築費の上昇などで首都圏の投資用マンションの発売戸数は減少しています。好立地で条件の優れた物件は希少性も高くなってきています。
新入社員の給与も30万円台となる企業も多く、賃料に余裕がある層にはより条件の良い住宅の需要も増えてくると考えられます。こうした供給減・需要増の中で投資用マンション市場も大きく変わっていくのではないでしょうか。
金利上昇は極めて穏やかなものであり、不動産市場に与える影響は軽微であると考えられます。今回の金利引き上げは日本の景気回復への本格的な第一歩ととらえて良いのではないでしょうか。