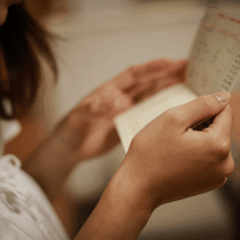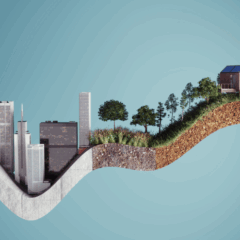インフレ時代に問われる“守りと攻め”の資産戦略。乱高下する株式市場と家計防衛のリアル
物価の上昇が止まらない——東京都区部の消費者物価指数は43ヵ月連続で上昇し、日常生活にじわじわと影響を与えています。加えて、米国発の「相互関税ショック」により株式市場は世界的に急落。家計の金融資産は過去最高を記録する一方で、その運用先として注目される株式や投資信託は不安定な局面に突入しています。
インフレ下では現金の価値が目減りし、投資先の選定がますます重要に。そんな中、内需中心で外的要因の影響を受けにくい“国内不動産投資”に再び注目が集まりつつあります。今、家計を守りながら資産を育てるために、私たちは何を選ぶべきなのでしょうか。
最新のデータが示すインフレの状況
最新のデータを見ても物価の上昇が続いている事が分かります。代表的な例の一つとして政府はお米の価格上昇の対策として備蓄米を放出しましたが、価格は高止まりしているようです。その背景にはお米の流通過程において不透明な部分も見え隠れしています。またガソリンなどの価格も高止まりの状況が続いており家計や物流にも影響が出ています。
インフレ時には買える物の価格が上昇しますので、実質的には現金の価値が目減りする事を意味します。総務省から毎月の物価上昇率が発表されていますが、この数値の分だけ現金の価値が減っていると言えますので、気になるところです。
東京都区部の消費者物価(速報)は2025年3月には総合指数が2020年を100とする指数で109.1となり、前年比2.4%の上昇で43ヵ月連続の上昇となりました。
給与水準は上昇していますが、物価上昇がそれを上回っていますので、実質賃金はマイナスの状況が続いています。つまり私達の給与は実質的に下がっていますので、何等かの対策が求められます。例えば資産運用、生活に身近な所ではポイ活などちょっとした努力の積み重ねが大切であると考えます。筆者は仕事でよく新幹線を利用しますが、東京~大阪間のグリーン車価格が19,000円超となりますが、JR東海のICカードなどを使うと片道で4,000円以上も得になります。これはほんの一例です。
◼︎消費者物価指数の推移(総合)
| 2024年 | 2025年 | ||||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 指数 | 106.9 | 107.2 | 107.7 | 108.1 | 108.2 | 108.6 | 109.1 | 108.9 | 109.5 | 110.0 | 110.7 | 111.2 | 110.8 |
| 前年同月比(%) | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 3.7 |
*2020年=100
家計の金融資産は過去最高、株式投資などが増加してきましたが
こうした状況の中でも、国民の金融資産は着実に増えてきていたようです。
日銀が発表した資金循環統計によると、家計の金融資産は2024年12月末時点で2,230兆円と過去最高となりました。前年同期比4.0%の増加です。
◼︎家計の金融資産の推移
| 2023年 | 2024年 | |||||||
| 3月末 | 6月末 | 9月末 | 12月末 | 3月末 | 6月末 | 9月末 | 12月末 | |
| 残高(兆円) | 2,053 | 2,114 | 2,121 | 2,144 | 2,186 | 2,212 | 2,179 | 2,230 |
家計の金融資産の内訳を見てみると、現金・預金が最も多く50.9%を占めます。
株価の上昇により株式が9.5%増加、また給与水準の上昇により現金も0.6%増加し1,134兆円と過去最高となりました。投資信託は前年比27.4%も増加しており、NISAなどを利用した投資信託への流入が多くなっている事が分かります。
株式は全体の13.4%を占め、年年比9.5%の増加となっています。つまり株式の割合が大きくなっている事が分かります。
しかしながら今回のトランプショックにより新しくNISAを始めた方々は特に落ち着かない状況となっているのではないでしょうか。
◼︎家計の金融資産の割合(2024年12月末)
| 残高 | 割合 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 金融資産計 | 2,230兆円 | 100% | 4.0% |
| 現金・預金 | 1,134兆円 | 50.9% | 0.6% |
| 債務証券 | 32兆円 | 1.4% | 11.8% |
| 投資信託 | 136兆円 | 6.1% | 27.4% |
| 株式等 | 298兆円 | 13.4% | 9.5% |
| 保険・年金・定型保証 | 544兆円 | 24.4% | 1.1% |
| その他 | 86兆円 | 3.9% | 20.5% |
トランプ大統領の「相互関税」の影響は?
このように家計の金融資産は株式にも大きく依存していますが、株式市場は今大きな局面を迎えています。
米国のトランプ大統領は2025年4月3日(日本時間)に輸入品の関税税率を引き上げる「相互関税」を発表し、4月9日13時(日本時間)から実施となり日本もからも24%の追加関税が適用となりました。国内の自動車や半導体などの輸出産業に大きな影響が出るほか、米国の物価が上がる可能性がありますので米国から輸入する商品・資材・エネルギー価格なども上がり、日本のみならず世界的なインフレが進む可能性があります。
株価への影響は大きい
今世界同時株安が進行しています。トランプ関税の影響で世界で株安が進んでおり世界の株式の時価総額の約1割に当たる1800兆円が消失したとの報道もあります。
2025年4月7日には株式市場にも大きく懸念が拡大し、一時日経平均株価が3万1,000円を割り込みワースト3に入る下げ幅となり1年半ぶりの水準となりました。もともとトランプ関税は想定内でしたが、その税率の上げ幅が市場の予想をはるかに超えた水準となっている事、米国の相互関税に対して中国が報復完全を発表した事から世界的な景気の減速が懸念される事も要因と考えられます。昨年2024年7月には日経平均株価4万2,000円台となりましたが1万以上下落している事になります。今回は短期で収束との楽観的な予想は難しく、日本の自動車メーカー「マツダ」などは早速アメリア生産拠点の一部を移す動きとなっています。
このように外的要因により株価が大きく変わってきています。家計の金融資産のうち投資信託・株式の割合は約37%にもなります。株価の大幅な下落によりこうした資産も減少してしまう可能性があります。さらにビットコインなどの仮想通貨も安値となっており、トランプショックは投資の世界にも大きな影響を与えています。
また4月9日には関税の一部停止の発表があり、10日の日経平均株価が大きく上昇するなど乱高下の様相を見せています。
筆者も長年株式投資をしていますが、基本的なスタンスとしては株価が大きく下落した局面において何回かに分けて株を購入しています。昨年の夏もそうでしたが、短期的な視点から見れば絶好の買場であったように、ここしばらくは株価の変動幅も大きく見方によっては面白い局面であると考えます。
金融市場への影響は
消費者物価の増加や大企業を中心としてですが給与水準も上昇してきている事もあり、日銀では2025年1月にも政策金利の引き上げを連続して行っています。
米国の雇用統計や関税による消費者物価指数の値上がりから短期的には金利の上昇が予想されますが、関税の影響が米国国民の消費に影響を与えるようになると、雇用にも問題が発生し、金利の低下→ドル安も想定されます。
一方日本国内においては、春闘、賃金アップ、消費の活性化→経済市場の好転という見方もありますが、製造業を中心とした産業の空洞化による雇用の減少→消費の低下という側面も否めません。
しかしこうした世界情勢により日本国内の経済の先行きも懸念されています。こうした事から日銀では今後の金利の引き上げには慎重となる事も予想され、不動産のローンを利用して不動産投資をする方にとってはむしろ好材料という見方もできます。
外的要因に強い業界は
上昇傾向にある株式市場ですが昨年8月にも大幅な下落となりましたが、これは日銀の利上げなどが要因となり、今回の下落は海外の要因が原因となりました。日本国内にも影響に大きいトランプ関税においては、今後各国の首脳による協調介入を始めとする大胆な対策も求められてきます。
一方、国内の株式市場をよく見てみると、内需中心を対象とするサービス業、鉄道、不動産など内需関連は関税の影響が受けづらいセクターで、株価に対する影響度は比較的低い状況となっています。このような時代背景から、内需中心の資産運用が改めて着目されるのではないでしょうか。
数ある内需の中心の中でも国内の不動産が主要な対象となると考えます。例えばマンション投資などは国内に建設したマンションを国内の人が購入し、国内の人が賃貸で借りるという基本構図(もちろん海外投資家、外国人の賃貸入居者も一定数いますが)があり、外的要因の影響を受けづらい投資対象と言える訳です。
どうして不動産投資は安定しているのか
過去においてはバブル崩壊やリーマンショック、ITバブル崩壊、新型コロナなど様々な経済ショックがありましたが、住宅の需要や賃料はその間も比較的、安定的に推移してきたと言えます。
マンションの賃貸契約の多くは2年となっており、その間の変動はほぼありません。つまりマンション投資は極めて安定した資産運用と言えます。
但しマンション業界全体で見てみると、東京を中心としたタワーマンションなどは海外の投資家及び国内の富裕層の購入割合が高く、株価下落による「逆資産効果」によって短期的には調整局面を迎える可能性もなきにしもあらずと考えます。
一方同じマンション業界でも投資向けのワンルームマンションなどは一定の単身者向けの住居として求められていますので短期的な影響は受けづらいと考えます。
インフレにより賃料も上昇傾向にありますので、将来のための資産運用としても極めて有望と言えます。
以上述べてきたように大きな経済変動がある時代の中でいつどういう場所にどういう投資をしたらいいかという着眼点に基づいて今後の皆様の資産運用の参考にしていただければ幸いです。