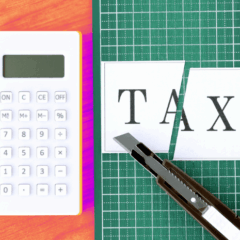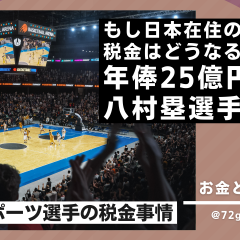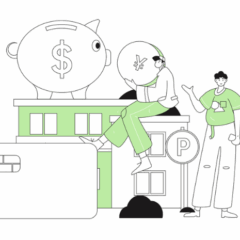新NISAでキャピタルフライトが始まるって本当?
2024年、NISAの制度が改正されて「新NISA」となりました。新NISAは、旧NISAよりも使い勝手がよくなったことから、これまで投資をしていなかった人も新たに投資を始める大きなきっかけになりました。
しかし、その新NISAが、日本から資金が大量に流出する「キャピタルフライト」の引き金になるという話もでています。
今回は、そもそもキャピタルフライトとは何かを確認した上で、新NISAがキャピタルフライトとどのような関係にあるのかを紹介します。
そもそも「キャピタルフライト」とは?
キャピタルフライトのキャピタルは「資本」、フライトは「飛行・逃避」という意味。キャピタルフライトは、国内の資金が外国に流出することをいいます。また、外国からの投資資金が一気に引き上げられたり、外国企業が国内から撤退したりすることもキャピタルフライトです。
キャピタルフライトは、政治的・経済的に不安定な新興国で発生することがあります。政府の財政が悪化した、経済危機が起きたとなれば、その国に投資している外国人投資家や外国企業は「このままこの国で投資(事業)をしているのは危険だ」と思うでしょう。そうして、投資資金を国外に移したり、その国での事業から撤退したりするのです。また、その国に住んでいる人も「自国の通貨が危ない」と思って、持っているお金の一部を米ドルやユーロなどといった比較的安定した通貨に両替することもあるでしょう。こうした動きがキャピタルフライトと呼ばれています。
キャピタルフライトの事例としては、アルゼンチンがよく知られています。
アルゼンチンは、1990年後半から政情不安と財政危機を抱えていました。2001年12月にアルゼンチンの国債が債務不履行(デフォルト)を起こし、翌月にそれまで続いていた固定相場制(1ペソ=1ドル)から変動相場制に移行すると、ペソの価値は3分の1程度に急落しました。このとき、アルゼンチン国内で事業を行った企業が一斉に引き上げました。国債も大暴落し、その後もたびたび債務不履行(デフォルト)を起こしました。
国債が暴落すると、財政赤字が膨らみ、負債が大きくなります。すると通貨がもっと安くなり、輸入するものの値段が上がるため、激しいインフレが起こります。そうして国の経済が崩壊していくと、さらなる通貨安を招き、資金が海外に逃避し、さらに通貨が安くなる…といった悪循環を招くのです。
本稿執筆時点(2025年2月16日)で、アルゼンチンのペソとドルの為替レートは、1ペソ=0.00095ドルとなっていました。つまり、ペソの価値は固定相場制時代の1000分の1以下になっています。
新NISAがキャピタルフライトの要因になるのか
このキャピタルフライトが、新NISAを発端に日本でも起きているのではないかという意見があります。
新NISAは、投資で得られた利益に通常かかる20.315%の税金を一生涯にわたって非課税にできる制度です。人気の投資先は、米国株型や全世界株型など外国株式型の投資信託です。投資信託の月間流出入額推移を分類別に見てみると、その勢いは明らかです。
<ファンド分類別 月間流出入額推移>
三菱アセット・ブレインズ「投信マーケット概況 2025年2月号(2025年1月末基準)」より
目立つのは深緑の「外国株式型」。どの月も総じてグラフが長い(資金が多く流入している=買われている)ことがわかります。オレンジの「国内株式型」と比べてみるとその差は一目瞭然です。
新NISAがスタートした2024年1月からはその傾向がさらに顕著になりました。新NISAを利用している日本人の多くが外国株式型を購入しているというわけです。
国内株式型はというと、2024年4月や8月はまだ健闘していますが、外国株式型には遠く及びません。5月・10月・12月にいたっては、マイナスになっています。この月は、国内株式型が買われた額より、売られた額のほうが多かった(資金が流出している)ことを表します。
外国株式型の投資信託を買うということは、「円売り」の要因になります。
たとえば、米国に広く投資する投資信託に月10万円ずつ積立投資するとします。このとき、投資信託のなかではこの10万円を米ドルに両替して(=円を売って米ドルを買って)、投資信託の資産を購入します。つまり1ドル=150円、手数料を考慮しないとして666ドルほどの円売りが毎月発生するのです。
また、新NISAの成長投資枠を利用して、1月に250万円分(成長投資枠240万円+つみたて投資枠1月分の10万円)投資するような人もいます。この場合は、1月に1万6666ドルもの円売りが発生します。2025年1月には2兆円を超える投資信託への資金流入がありますが、そのほとんどが外国株式型ですから、ドル売りの圧力も大きなものがあります。
新NISAの年間の非課税投資枠は最大で360万円で、生涯投資枠は1800万円です。今後も、外国株式型の人気が続けば「円を売ってドルを買う」動きが続くことになると考えられます。実際、新NISAで人気の「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」やオルカンの愛称で知られる「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」には、毎月1000億円を超える資金流入があります。
ただ、「キャピタルフライト」と指摘するのは違うと考えています。キャピタルフライトは自国の政治・経済や通貨の信頼性がないから、資金を他国に逃避させることです。
多くの日本人が、日本がヤバイから外国に資金を逃避し資産を購入しているというわけではなく、日本株に投資よりも、米国をはじめとする外国株の方が投資リターンは大きいと考えているから投資をしているだけに過ぎません。「資産逃避」ではなく、「資産移転」であり、あくまでも「未来への投資」です。
とはいえ、円を売って外貨を買う動きは、円安(外貨高)の要因です。つまり、新NISAでの投資が浸透すればするほど、円を売って外貨を買う動きが進むわけですから、円安圧力があるということは否めないでしょう。
デジタル赤字も円安の要因に
新NISAに加えて、デジタル赤字も円安の要因になりえます。デジタル赤字とは、日本の個人や企業が海外のデジタルサービスを利用することで生じる赤字です。今やグーグル、アマゾン、マイクロソフト、アップルといった米国企業のサービスを誰もが利用しています。その利用金額が、米国の個人や企業が利用する日本企業の利用金額より少なければ「デジタル赤字」となります。
三菱総合研究所の調査によると、こうしたデジタル赤字は年々増加しており、2024年には6.7兆円に達しています。米国のサービスを利用するときには、円を売って米ドルを買ったうえで利用するのですから、デジタル赤字が拡大すると円安になると考えられます。
日本の円安の要因はキャピタルフライトではない?
近年、日本では急激な円安が進行しました。ただ、それはキャピタルフライトが起こったからではありません。円安の主な要因は、金利差です。
<米ドル/円の為替レート(2022年〜2025年2月)>
(株)Money&You作成
米ドル/円の為替レートは2016年〜2022年初頭まで、おおむね1ドル100円〜120円のレンジで推移していました。しかし、2022年2月にロシアによるウクライナ侵攻がはじまると、ロシア産のエネルギーや穀物などの供給が激減したため、世界的にインフレが進行しました。
それまで、コロナ禍による景気刺激策として政策金利を下げていた世界の中央銀行は、インフレを抑えるために政策金利をハイペースで引き上げました。米国も、2022年5月から2023年7月にかけて合計11回もの利上げを行い、政策金利を「0.25%〜0.5%」から「5.25%〜5.5%」まで引き上げています。米ドルと円の金利差(2年もの国債利回りより算出)が大きくなるタイミングと為替レートが円安(ドル高)になるタイミングも、おおよそ連動している様子が見て取れます。
日本の中央銀行、日銀は長らくマイナス金利政策を維持し、政策金利を上げずにきました。そのため、日本と米国をはじめとする各国の通貨の金利差が拡大していきました。持っていてもほとんど金利のつかない円と、5%の金利のもらえる米ドル、どちらが欲しいかといえば、ほとんどの人が米ドルと答えるでしょう。こうした金利差を背景に、為替レートは(途中、為替介入などで一時的に円高になる場面こそありますが)総じて円安方向に動いてきたのです。
2024年3月になって、日銀はマイナス金利を解除しました。以後、2024年7月、2025年1月と利上げを行ったことで、日本の政策金利も0.5%となりました。今後どうなるかはわかりませんが、さらなる利上げも視野に入っています。一方で米国は2024年後半になって利下げを実施。インフレが鈍化してきたことや、景気悪化の防止などがその背景にあると言われています。
つまり、日本と米国の金利差は縮小することになります。これは円高(ドル安)の要因です。グラフを見ると、「大きな円安トレンドが終わった」とまではまだ言い切れませんが、日銀の利上げと米国の利下げによって短期的に円高に動く場面も出てきています。
BIS(国際決済銀行)が3年に1度実施している「世界外国為替市場調査」(2022年)によると、2022年4月時点の1日あたりの取引額はおよそ7.5兆ドルで、日本円のシェアは8.3%となっています。外国為替市場では、1日で約0.62兆ドル、1ドル=150円で換算して93兆円の取引が行われている計算です。2025年1月の新NISAによる外国株式型の投資信託の購入額は1か月で約2兆円、デジタル赤字も1年間で6.7兆円ですから、外国為替市場の規模は桁違いに多いことがわかります。
では、今後日本でキャピタルフライトが起きるのか
最初に紹介したとおり、キャピタルフライトは政治的・経済的に不安定な新興国で発生するものです。
日本の「国の借金」は2024年末時点で1317兆円と確かに多いのですが、その借金の多くは国内(日銀・銀行・生損保・年金・家計)が保有している国債などでまかなわれています。また、日本と海外のものやサービスの取引状況を示す経常収支はずっと黒字を維持しており、2024年は過去最大となる29兆2615億円の黒字になっています。
外国人観光客も2024年で3687万人と過去最多を更新。円安によって日本での旅行がしやすいのがその大きな要因ですが、治安がよく、政情不安もないことも訪日を後押ししています。また、熊本に台湾の半導体メーカー、TSMCの工場ができるなど、外資系企業の誘致も進んでいます。
日本でキャピタルフライトが起こっている(近々起こる)ということは、考えにくい状況だと思います。
しかし、今後日本経済が暗礁に乗り上げ、円安が進み、投資の魅力度が薄いことが続いていけば、いずれキャピタルフライトが起こる可能性がないとはいえないでしょう。
私たちができることは、どんな未来になったとしても対処できるよう、また将来時点での人生の選択肢を増やせるように、資産配分を考え、分散投資を愚直にやり続けていくことだと思います。
勤労収入は「円」、預貯金などの安全資産も「円」です。外国資産に投資をしていなければ、100%「円」に投資しているようなものです。「外国資産」に投資することは、分散投資の観点からも、世界経済の成長の恩恵を受けるという観点からも合理的かつ経済的ではないでしょうか。
頼藤 太希(よりふじ・たいき) マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki