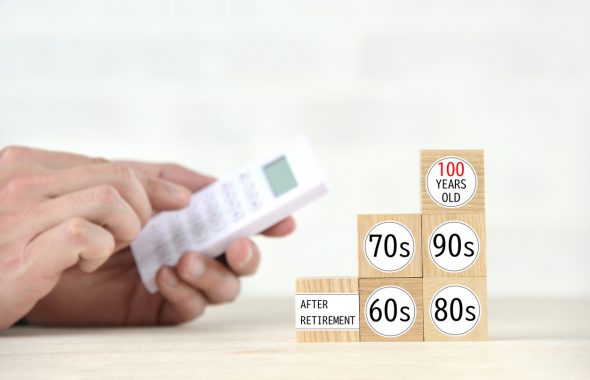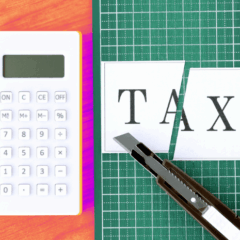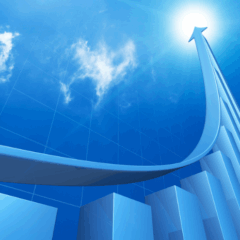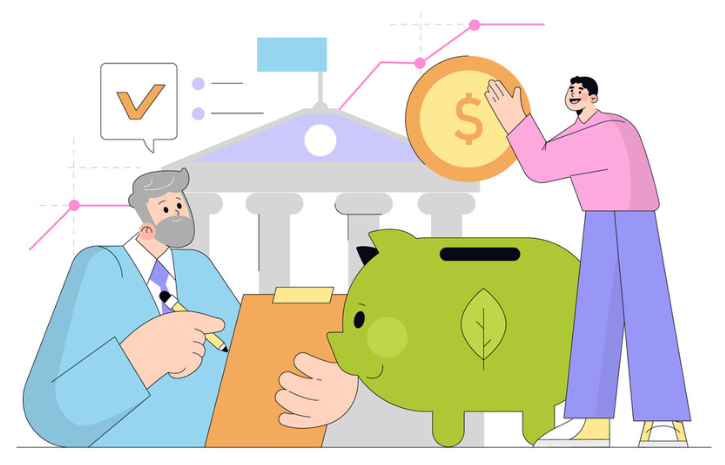
年金は一生涯でいくら納めて、65歳から90歳まででいくらもらえるのか
「年金なんて納めてもどうせ元が取れない」という声を耳にします。確かに、年金の保険料は決して安くはないですし、老後にもらえる年金だけで生活するのは難しい金額かもしれません。しかし、「元が取れない」は本当なのでしょうか。保険料を支払うことで、将来いくら年金がもらえるか、知らずに言っていませんか?
今回は、国民年金・厚生年金の一生涯の保険料と、保険料を支払うことでもらえる年金額の例を紹介します。
そもそも国民年金・厚生年金とは?
日本の公的年金には、国民年金と厚生年金の2種類があります。
国民年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入する年金です。40年間にわたって所定の国民年金保険料を支払えば、誰でも満額の年金を受給できます。
厚生年金は、会社員や公務員が勤務先を通じて加入する年金です。会社員や公務員は、毎月の給料から厚生年金保険料が天引きされています。厚生年金保険料には、国民年金保険料も含まれています。したがって、会社員や公務員は厚生年金に加えて国民年金ももらえます。
公的年金から受給できる年金には、大きく分けて下記3つがあります。
- 老齢年金…原則65歳からもらえる年金
- 障害年金…所定の障害を負ったときにもらえる年金
- 遺族年金…亡くなった人の配偶者や子などがもらえる年金
今回紹介するのは老齢年金です。老齢年金には、国民年金からもらえる「老齢基礎年金」と、厚生年金からもらえる「老齢厚生年金」があります。
国民年金はいくら納めていくらもらえる?
国民年金保険料は、誰でも同じです。年度により増減があり、近年は増額傾向にありますが、2025年度の場合は月1万7510円です。この金額を20歳から60歳までの40年間(480か月)にわたって納めたとすると、国民年金保険料の総額は840万4800円となります。
- 1万7510円×480か月=840万4800円
国民年金から受給できる老齢基礎年金の金額は、国民年金保険料の納付月数が480か月に達していれば、誰でも満額にできます。
65歳から老齢基礎年金を受給する場合、満額は年83万1700円(2025年度)です(1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方の場合、老齢基礎年金の満額は年82万9300円ですが、計算を簡略化するために、以下は年83万1700円で計算しています)。
仮に、65歳から90歳まで、25年間老齢基礎年金を受給した場合、総額は2079万2500円となります。
- 83万1700円×25年=2079万2500円
厚生年金はいくら納めていくらもらえる?
厚生年金の保険料は基本的に、給料が多ければ多いほど保険料が増えます。
たとえば、給料が月30万円の場合、厚生年金保険料は月5万4900円です。この金額には、国民年金保険料も含まれています。実際は「労使折半」といって、半額は勤め先の会社が負担してくれているため、自己負担額は月2万7450円です。
仮にこの金額を社会人になった22歳から65歳までの43年間支払っていたとすれば、厚生年金保険料の総額は1416万4200円となります。
- 2万7450円×12か月×43年間=1416万4200円
厚生年金から受給できる老齢厚生年金の受給額は「平均標準報酬月額×給付乗率×加入月数」で計算します。どの数字も人により異なるので、金額も人それぞれ変わります。
平均標準報酬月額が30万円、給付乗率が0.005481、厚生年金加入期間が43年間(516か月)だとすると、老齢厚生年金の金額は30万円×0.005481×516か月=84万8458円と計算できます。これに加えて老齢基礎年金も受け取れるので、1年に受け取れる年金額の合計は84万8458円+83万1700円=168万158円となります。
この金額を、65歳から90歳までの25年間にわたって受け取った場合、合計額は4200万3950円となります。
- 168万158円×25年=4200万3950円
今回の試算をまとめると、
【国民年金】
- 20歳〜60歳で合計840万4800円の保険料を支払う
→65歳から90歳までの25年間で、老齢基礎年金が合計2079万2500円もらえる
保険料と年金額の差額…1238万7700円
【厚生年金(国民年金含む)】
- 22歳〜65歳で合計1416万4200円の保険料を支払う
→65歳から90歳までの25年間で、老齢基礎年金と老齢厚生年金合わせて合計4200万3950円もらえる
保険料と年金額の差額…2783万9750円
こうみると、支払う金額よりも、もらえる年金額の方がずいぶん多いことがわかります。しかも、今回90歳まで年金をもらう計算にしていますが、95歳、100歳と長生きすれば、もらえる年金額の合計はさらに増加します。
「何歳まで生きるか」は誰にもわかりませんが、65歳から老齢年金を受け取り開始した場合、国民年金は約10.1年間、厚生年金(国民年金含む)は約8.4年間もらうと、受け取る老齢年金額合計が支払った年金保険料合計を上回ります。仮に65歳から年金を受給した場合、厚生年金なら73歳〜74歳、国民年金でも75歳程度まで生きれば元が取れる計算です。
日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.14歳ですし、2023年時点で65歳の人の「平均余命」はおおよそ男85歳、女89歳(厚生労働省「令和5年簡易生命表」より)となっています。そう考えると、支払った保険料の元が取れる可能性は十分あるでしょう。年金は、長生きリスクに対応した「保険」の役割を果たしているのです。
年金・老後資金を増やす7つの方法
「年金は元が取れる」とはいっても、大切なのはやはり老後の生活です。元が取れるからといって、年金額が少ないのでは心許ないですね。そこで、年金を増やしたり老後資金を増やしたりできる方法を紹介します。
◼︎年金・老後資金を増やす方法1:国民年金に任意加入する
国民年金の加入期間は20歳から60歳までの40年間(480か月)と紹介しました。保険料を納めていない期間がある場合、2年以内であれば後から納めることができますが、それを過ぎてしまうと「未納」の扱いになってしまいます。保険料が未納のままだと、その分もらえる老齢基礎年金が減ってしまいます。
また、国民年金保険料の支払いが難しい場合には免除や猶予が受けられますが、この場合も10年以内に保険料を納めないと、もらえる老齢基礎年金が本来より減ってしまいます。
加入期間が40年に満たないのであれば、国民年金に任意加入できます。任意加入では、60歳〜65歳までの5年間、自分で国民年金保険料を支払うことで、国民年金保険料の加入期間を増やすことができます。加入期間が1年間増えると、老齢基礎年金は年約2万円増える計算。加入期間が40年に達したら、老齢基礎年金を満額もらうことができますし、40年に達しなくても、もらえる年金額を増やすことができます。
忘れやすいのは学生の間の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用していた人。学生納付特例制度で猶予してもらった保険料も、10年以内であれば追納ができます。しかし、厚生労働省の資料によると、2014年中に追納をした人の割合はわずかに8.9%となっています。老齢基礎年金を増やすためにも、追納をしましょう。
◼︎年金・老後資金を増やす方法2:付加年金に加入する
付加年金は、国民年金に加入している方を対象とした年金の上乗せ制度です。国民年金保険料に月400円上乗せして付加保険料を支払うことで、老齢基礎年金の金額が「200円×付加保険料納付月数」分増えます。
60~65歳までの5年間付加年金に加入すると、2万4000円の付加保険料で老齢基礎年金が年1万2000円増やせます。年金を2年以上受け取ると元が取れ、以後もその増額分を受け取れます。
◼︎年金・老後資金を増やす方法3:60歳以降も働く
国民年金の加入は原則60歳までですが、厚生年金は70歳まで加入でき、厚生年金保険料を納めることができます。60歳以降も厚生年金に加入して働くことで、老齢厚生年金が増えます。
老齢厚生年金の増加額は年収と加入期間により異なります。
◼︎60歳以降も働いた場合の年金増加額早見表(年額)
たとえば、60歳以降年収300万円で10年間働いた場合、もらえる年金額は年16.4万円増える計算。仮にその後20年間年金をもらったら、年金額に328万円の差が生じます。
60歳以降も働くと、給与や賞与などの収入も得られます。勤め先の健康保険にも加入できるので、保険料も抑えることができます。そのうえ、老齢厚生年金も増えるのですから、メリットが大きいでしょう。
◼︎年金・老後資金を増やす方法4:年金を繰り下げ受給する
老齢年金の受け取りを66歳~75歳の間に遅らせる「繰り下げ受給」をすると、年金額が増えます。繰り下げ需給では、受給開始を1か月遅らせるごとに、受け取れる年金額が0.7%ずつ増加。最大で75歳まで繰り下げることで年金額が84%増加します。
65歳時点の年金額が月10万円(年120万円)の人が70歳まで年金を繰り下げたら、年金額は42%増えて月14万2000円(年170万4000円)、75歳まで繰り下げたら年金額は84%増えて月18万4000円(年220万8000円)に増えます。
60歳以降も働いていれば収入があるので、年金の繰り下げ受給も比較的選びやすいでしょう。年金が増えれば、老後の資金計画も立てやすくなります。
◼︎年金・老後資金を増やす方法5:iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)に加入する
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、自分で出した掛金を自ら選んだ商品で運用し、老後(原則60歳以降)にその成果を受け取るしくみです。
iDeCoでは、掛金が全額所得控除になるため、毎年の所得税や住民税を安くできます。そのうえ、運用で得られた利益にかかる税金が非課税にできます。さらに、一時金・年金として受け取るときにも税制優遇が受けられます。国民年金・厚生年金の上乗せとなるお金を用意するのに向いている制度です。
たとえば、企業年金のない会社員(毎月の掛金上限2万3,000円)がiDeCoで毎月2万円の掛金を出して、積立投資した場合、年間の掛金の合計額24万円が全額所得控除の対象になります。この人の所得税率が5%(住民税率は一律10%)だった場合、毎年所得税が年1万2000円、住民税が2万4000円、合計3万6000円の税金を減らすことができます。これが30年間続いたら、軽減できる税金の合計は108万円に。大きな節税効果が得られます。
なお、iDeCoの掛金上限は今後引き上げられる予定。より多く掛金を出せれば、その分節税効果も大きくなり、老後資金を手厚く用意できるようになります。
◼︎年金・老後資金を増やす方法6: NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)を利用する
NISAは投資で得られた利益にかかる税金をゼロにできる制度。2024年に制度が改正されて「新NISA」と呼ばれ、話題になっています。
新NISAでは、積立投資専用の「つみたて投資枠」と、積立投資だけでなく一括投資もできる「成長投資枠」の2つの投資枠を利用して投資ができます。そして、運用で得られた利益にかかる税金が一生涯にわたって非課税の投資ができます。
iDeCoのように所得税や住民税を安くするメリットはないのですが、新NISAの資産はいつでも引き出せるうえ、生涯にわたって投資ができるので、使い勝手がよいでしょう。
◼︎年金・老後資金を増やす方法7:国民年金基金に加入する
自営業・フリーランスといった国民年金の第1号被保険者には、厚生年金がありません。この厚生年金にあたる部分を自分で作る制度が国民年金基金です。
国民年金基金では、毎月一定額の掛金を支払うことで、老後に年金を受け取ることができます。国民年金基金では、終身年金をベースに、一定期間受け取れる確定年金を組み合わせることもできます。
ただし、付加年金とは併用できず、iDeCoと掛金の枠を共有(2025年時点では、月額6万8000円)する点には注意が必要です。
「年金なんて納めてもどうせ元が取れない」ということはありません。それどころか、年金は老後の長生きを支える収入の柱になります。今回紹介した年金・老後資金を増やす方法を取り入れて、少しでも老後資金を多くしておけば、その収入の柱も太くなり、より老後生活を安心して送れるようになるでしょう。できるところから1つずつ、取り組んでみてください。
頼藤 太希(よりふじ・たいき)
マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)
X(旧Twitter)→ @yorifujitaiki